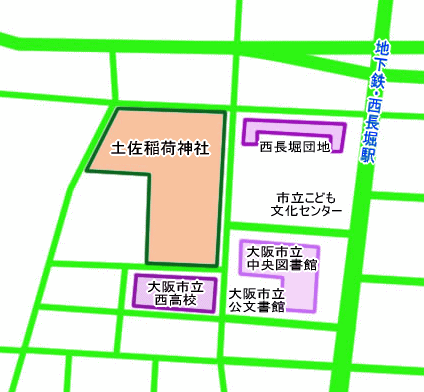大阪の大阪メトロ「西長堀駅」すぐにある土佐稲荷神社に行ってきました。
土佐稲荷神社と言えば、京都にも土佐稲荷・岬神社という神社がありました。京都の方は本当にに小さな神社ですが、大阪の土佐稲荷は大きな神社です。
この場所は江戸時代には土佐藩大坂蔵屋敷で、明治時代になると岩崎弥太郎邸となりました。それでは出発しましょう!
江戸時代、土佐藩蔵屋敷境内に土佐稲荷神社があった
場所は大阪メトロ「西長堀駅」。この駅は細長い駅なのです。
千日前線だとまだ近いのですが、鶴見緑地線からの場合、地下道を結構歩かないといけないので要注意です。一駅分ぐらいありそうですよ。
地上にでると目印として、大阪市立中央図書館があります。
その図書館からは西に歩くと広場が見えてきます。これは土佐公園と呼ばれています。
それを北に上がると鳥居が顔をのぞかせています。写真は土佐稲荷神社の東側。
土佐稲荷神社正面。
これを見た時、想像していたより大きな神社だったのでビックリしました。それもそのはず、ここは当時、土佐藩邸(土佐藩・大坂蔵屋敷)だったのです。
江戸時代、ここから北に離れた場所にある中之島周辺にはたくさんの藩邸がありましたが、土佐藩だけは中之島には無く、この場所、堀江にありました。
土佐藩・山内家が参勤交代で大阪を通過するときは、まずこの土佐藩邸に立ち寄っていました。その土佐藩邸の一角に土佐稲荷神社があったのです。
土佐藩邸がある場所には必ず土佐稲荷神社を造っています。それは京都の土佐藩邸も同様です。
伏見稲荷の分霊を祀り、町人の参拝も許されていたそうです。
鳥居からの参道。
土佐藩の家紋がありました。
境内に三菱マークが見られる
では参拝します。ビックリしたのは賽銭箱に三菱のマークが!神社に企業のマークがあるなんて、なんか不思議な感じですね。
その屋根のところにも三菱マークがありました。
そう言えば入り口付近も三菱グループの会社だらけでしたよ。境内に停車していた車ももちろん三菱でした(笑)。
明治時代になり土佐稲荷神社は岩崎弥太郎の民有地になる
幕末に土佐藩で商売を担当した岩崎弥太郎は、この土佐藩邸の向かいの家に住みはじめました。
そして明治に入り廃藩置県で払い下げとなり、岩崎弥太郎の民有地となっています。つまり、この場所は三菱グループの原点と言えますね。
上の写真は土佐稲荷内にある「岩崎屋舊邸址(岩崎屋旧邸跡)」碑。この碑の横には以下のような説明文があります。
江戸時代、ここは土佐藩邸でしたが、明治となり『三菱』の創業者である岩崎弥太郎がこれを引き継ぎ、以降岩崎家の土地として彌太郎もこの一画に居を構えました。
最後に
私自身、大阪に住んでいながら、土佐稲荷神社のことを知りつつも、これまで行った事がありませんでした。
龍馬伝にも岩崎弥太郎が登場したりと、坂本龍馬と岩崎弥太郎に関心を持った人も多いかと思います。
ここは桜の名所でもあります。関西に住んでいる人は、近場から散策してみてはいかがでしょうか。
関連:[土佐藩]幕末の史跡一覧に戻る